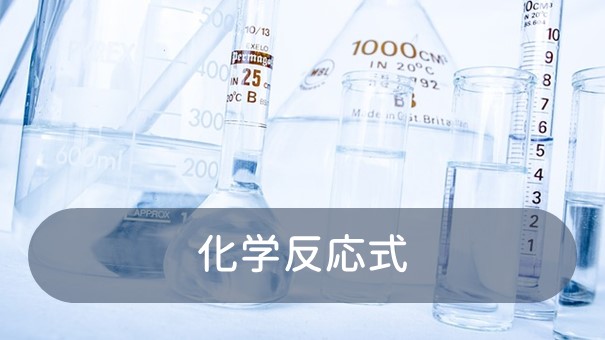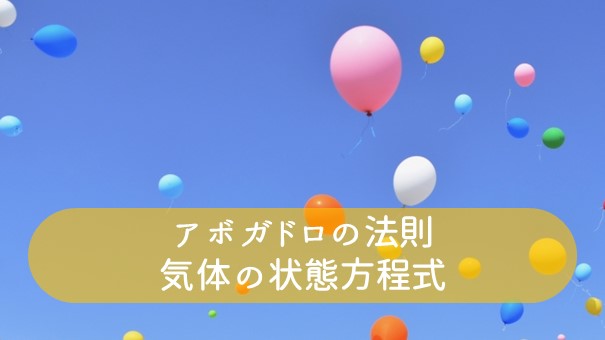化学反応式:反応前の化学式と反応後の化学式の関係性を示したもの
化学反応式の書き方
化学反応式を書くには3つのルールを覚えることが重要です。
ここでは、化学反応式のルールについて確認していきましょう。
出発物質(反応前の物質)は左辺
生成物質(反応後の物質)は右辺
左辺と右辺をつなぐのは右矢印(→)
左辺と右辺の原子数が等しくなるように係数をつける
→反応前後で原子は生成・消滅しない
係数は整数とする
係数が1の場合は1を省略する
触媒のような反応を促進する物質は式に含めない
触媒自体は反応前後で変化しない
では、上のルールを基に化学反応式を書いてみましょう。
例)炭酸水素ナトリウムを加熱すると炭酸ナトリウムと水と二酸化炭素になる
<ルール1>
従い左辺に出発物質、右辺に生成物質を書き、→で繋ぎます。
NaHCO3→Na2CO3+H2O+CO2
<ルール2>
係数をつける
2NaHCO3→Na2CO3+H2O+CO2
<ルール3>
触媒は書かない(今回は該当なし)
2NaHCO3→Na2CO3+H2O+CO2
係数をつける時のポイント
左辺・右辺とも1つの化合物にしか含まれない原子を探す
→上の例ではNaとHが該当します
選んだ原子の数が一致するように化合物に係数をつける
→上の例では、Naに注目するとNaHCO3には1個、Na2CO3には2個
→NaHCO3の係数は2、Na2CO3の係数は1とします
→→Hに注目するとNaHCO3には1個、H2Oには2個
→→NaHCO3の係数は2、H2Oの係数は1とします
他の原子を確認して同じように数を合わせる
→上の例ではCの数が左右であっていることを確認します
化学反応式を書いてみる
身近な?反応について、化学反応式で表してみましょう。

↓↓↓ 答えを確認 ↓↓↓