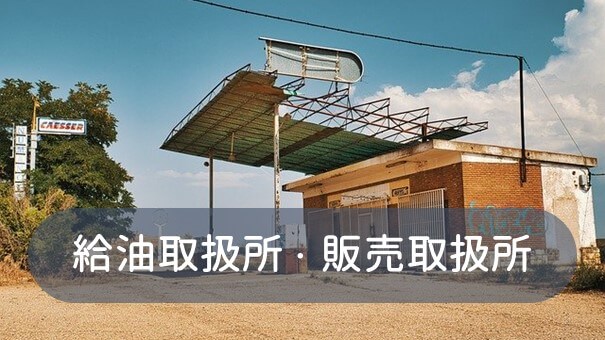スポンサーリンク
消防設備:消火設備は第1種~第5種に分類されます
※危険物の第1種~第6種とは違いますので注意しましょう
所要単位:製造所等に対してどの程度の消火能力の消火設備が必要かを定める基準単位
能力単位:所要単位に対する消火設備の消火能力の基準単位
警報設備:指定数量の倍数が10以上を扱う場合に必要
消防設備
消防設備の分類
危険物を扱う施設では、火事に備えた消火設備が必要です。
消火設備は第1種~第5種に分けられています。
| 種別 | 消火設備 |
| 第1種消火設備 | 屋内消火栓設備 or 屋外消火栓設備 |
| 第2種消火設備 | スプリンクラー設備 |
| 第3種消火設備 | 水蒸気・水噴霧、泡、ハロゲン化物、二酸化炭素、消火粉末など |
| 第4種消火設備 | 大型消火器 |
| 第5種消火設備 | 小型消火器、水バケツ・水槽、乾燥砂、膨張ひる石・膨張真珠岩 |
危険物と消火設備の関係はこちらで確認できます。
Mt.フジ
基本的には第1種~第5種の消火設備について覚えましょう。
第1種消火設備

第2種消火設備

第3種消火設備

第4種消火設備

第5種消火設備

所要単位と能力単位
所要単位とは《製造所等に対してどの程度の消火能力の消火設備が必要かを定める基準単位》のことです。
能力単位は《所要単位に対する消火設備の消火能力の基準単位》のことです。
能力単位は消火設備によって数字が決まっています。
所要単位が『10』である設備には、合計の能力単位が『10』以上になるように消火設備を設ける必要があります。
ex) 3能力単位×4設備=12所要単位
なお所要単位は、製造所等の種類・火災に対する構造・延べ面積(又は指定数量の倍数)で決まっています。
耐火構造と不燃材料を比較すると、耐火構造のほうが1所要単位あたりの面積が2倍広くなります。
つまり、耐火構造の方が消火設備は少なくてよいということになります。
| 製造所等の構造 | 1所要単位あたり | |
| 製造所・取扱所 | 耐火構造 | 100 m2 |
| 不燃材料 | 50 m2 | |
| 貯蔵所 | 耐火構造 | 150 m2 |
| 不燃材料 | 75 m2 | |
| 屋外の製造所等 | 外壁を耐火構造とし、かつ水平最大面積を建坪とする建物とみなして算定する | |
| 危険物 | 指定数量が10倍毎 | |
警報設備
指定数量の倍数が10を超える危険物を扱う施設は警報設備を設置する必要があります。
警報設備とは《自動的に作動する火災報知器設備、拡声装置、消防機関に通報できる電話、非常ベル、警鐘》のことです。
Mt.フジ
本日はこのへんで、みなさんごきげんよう!
![]()