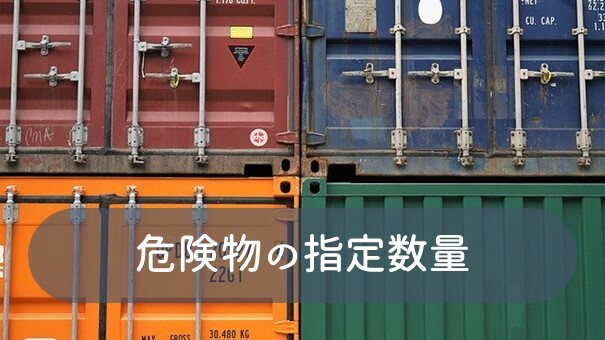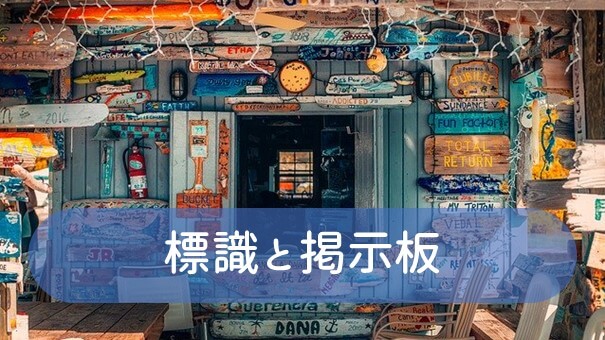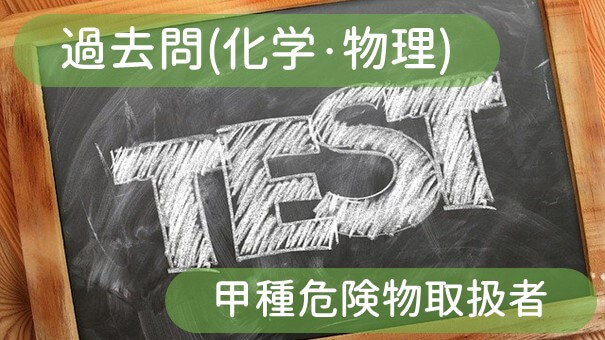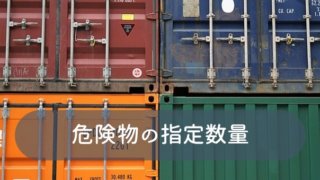危険物の分類
・消防法では第1類~第6類に分類される
・常温(20℃)・常圧下で固体または液体であり、気体はない
第4類危険物
・引火点の違いで7種類に分類される
・250℃以上の引火点を持つ物質は消防法ではなく市町村条例で規制される
危険物の分類
消防法
危険物とは、別表第1の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう
| 種別 | 性質 | 概要 | 物質の例 |
| 第1類 | 酸化性固体 | そのもの自体は燃焼しない 他の物質を強く酸化させる固体 可燃性と混合したとき、熱、衝撃、摩擦、により分解し、きわめて激しい燃焼を起こす |
塩素酸塩 (塩素酸カリウム)過塩素酸塩 (過塩素酸ナトリウム)無機過酸化物 |
| 第2類 | 可燃性固体 | 火炎により着火しやすい固体 比較的低温で(40℃未満)で引火しやすい固体 出火しやすく、かつ、燃焼が速い 燃焼の時に有毒ガスを発生するものがある |
赤リン
硫化リン 硫黄 金属粉 |
| 第3類 | 自然発火性物質 および禁水性物質 の固体または液体 |
空気にさらされることにより自然発火 水と接触して発火 または可燃性ガスを発生する |
カリウム
ナトリウム 黄リン |
| 第4類 | 引火性液体 | 引火性のある液体 | 特殊引火物
アルコール類 石油類 動植物油類 |
| 第5類 | 自己反応性物質
の固体または液体 |
加熱分解などにより比較的低い温度多量の熱を発生、または爆発的に反応する | ニトロ化物(ピクリン酸)
硝酸エステル |
| 第6類 | 酸化性液体 | そのもの自体は燃焼しない液体 混在する他の可燃物の燃焼を促進する |
過塩素酸
硝酸 過酸化水素 |
危険物第1類:酸化性固体
それ自身は燃焼しませが、他の物質を強く酸化させる性質を持ちます。
また、可燃性の物質を混合したとき、熱や衝撃、摩擦により分解し、極めて激しい燃焼を起こします。
代表的な物質
塩素酸塩(塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウムなど)
過塩素酸塩(過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウムなど)
過マンガン酸塩(過マンガン酸ナトリウム、過マンガン酸アンモニウムなど)
危険物第2類:可燃性固体
火炎により着火しやすい性質を持ちます
また、比較的低温(40℃未満)で引火しやすい固体も含まれます
着火しやすいということで、出火しやすく、出荷した場合の燃焼速度は速いです。
また、燃焼時に有毒ガスを発生するものもあります
代表的な物質
赤リン
硫化リン(三硫化リン、五硫化リン、七硫化リン)
硫黄
鉄粉や金属粉(アルミニウム粉、亜鉛粉)
マグネシウム
危険物第3類:自然発火性物質及び禁水性物質(固体又は液体)
自然発火性物質とは、空気にさらされることにより自然発火する物質です。
禁水性物質とは、水と接触することにより発火する物質を言います
また、これらが燃焼する際には可燃性ガスを発生する場合があります
代表的な物質
黄リン
アルカリ金属(リチウム、ナトリウム、カリウム)
アルカリ土類金属(カルシウム、バリウム)
危険物第4類:引火性液体
読んで字の通り、引火性のある液体です。
代表的な物質
引火点の温度により7種類に分類される
| 区分 | 性質 | 代表的な物質 |
| 特殊引火物 | 1気圧で発火点が100℃以上、又は引火点が-20℃以下で沸点が40℃以下のもの | ジエチルエーテル 二硫化炭素 アセトアルデヒド |
| 第1石油類 | 1気圧で引火点が21℃未満 | ガソリン ベンゼン トルエン アセトン 酢酸エチル |
| アルコール類 | 炭素数3までの飽和1価アルコール | メタノール(メチルアルコール) エタノール(エチルアルコール) プロパノール(n-プロピルアルコール) |
| 第2石油類 | 1気圧で引火点が21℃以上70℃未満 | 灯油 軽油 酢酸 キシレン |
| 第3石油類 | 1気圧で引火点が70℃以上200℃未満 | 重油 グリセリン ニトロベンゼン クレオソート油 |
| 第4石油類 | 1気圧で引火点が200℃以上250℃未満 | ギヤー油 シリンダー油 タービン油 潤滑油 |
| 動植物油類 | 動物の脂肉や植物の種子などから抽出 引火点が250℃未満 | イワシ油 アマニ油 ヤシ油 ゴマ油 |

危険物第5類:自己反応性物質(固体又は液体)
加熱分解などにより比較的低い温度で多量の熱を発生、または爆発的に反応する性質を持ちます
代表的な物質
硝酸エステル(硝酸メチル、硝酸エチル、ニトログリセリン)
ニトロ化合物(ピクリン酸、トリニトロトルエン)
有機過酸化物(過酸化ベンゾイル)
危険物第6類:酸化性液体
それ自体は燃焼しませんが、混在する他の可燃物の燃焼を促進する性質を持ちます
代表的な物質
過塩素酸
過酸化水素
硝酸