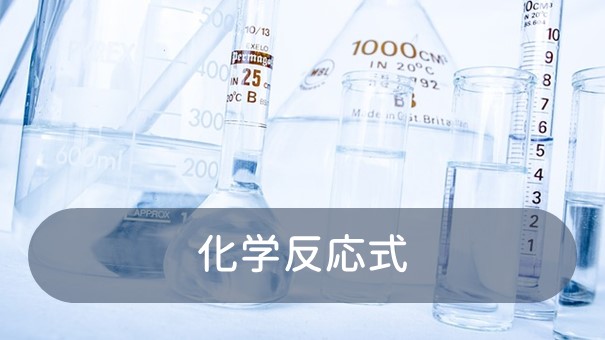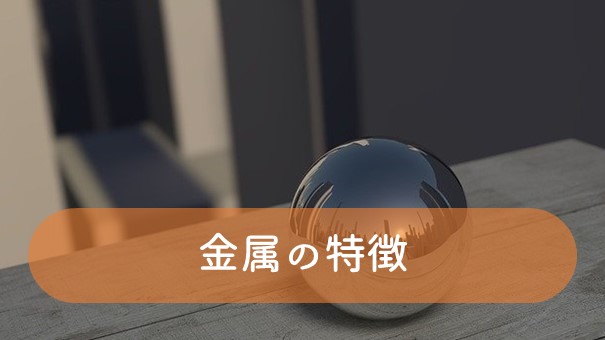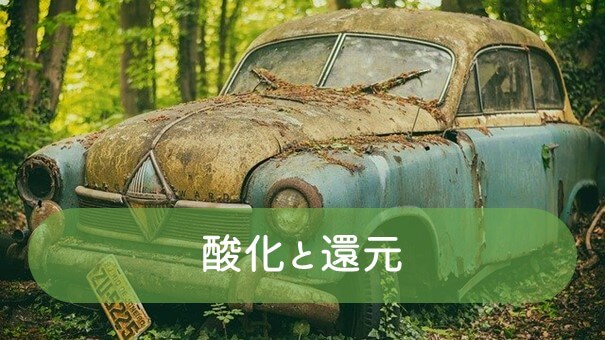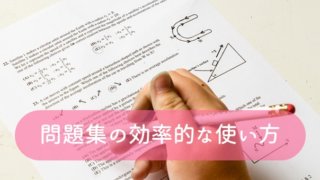溶媒:他の物質を溶かす液体
溶質:溶媒に溶ける物質
溶液:溶媒に溶質が溶けた状態
溶解度:溶質が溶媒に溶ける度合い
ヘンリーの法則:一定温度条件下において一定量の溶媒に溶ける気体の質量は圧力に比例する
溶解
溶解とは《液体に他の物質が溶けて均一な状態になること》です。
溶解を理解するためには、溶媒・溶質・溶液を区別して使えるようにしておくことが重要です。
溶媒は他の物質を溶かす液体
溶質は溶媒に溶ける物質
溶液は溶質が溶媒に溶けた状態
のことです。
このうち、溶媒が水である溶液を水溶液と言います。
塩化ナトリウムを水に溶かしてできる食塩水(塩化ナトリウム水溶液)について、溶媒・溶質・溶液に分けてみましょう。
↓ ↓ ↓ 答え ↓ ↓ ↓
A. 溶媒=水 , 溶質=塩化ナトリウム , 溶液=食塩水

溶解度
溶解度とは《溶質が溶媒に溶ける度合い》のことです。
溶質が固体の場合、溶媒100 gに溶ける溶質の質量(g)のことを指します。
つまり、物質Aの溶解度が5(g/100 g)の場合、溶媒100 gには物質Aが5 g、溶媒200 gには物質Aが10 g溶けるということです。

溶質が気体の場合、1気圧条件下で溶媒100 gに溶ける気体の質量(g)または体積(L)のことを指します。
ここでもう一度食塩水を例に考えてみましょう。
水に塩化ナトリウムを溶かすと食塩水ができます。
では、どんどん塩化ナトリウムを追加していったらどうなるでしょうか?
追加していくと溶けなかった(溶解しなかった)塩化ナトリウムが底に沈んでいきます。
水には溶かせる塩化ナトリウムの量に限界があり、限界点(ギリギリ溶ける量)を溶解度と言います。
限界点は溶媒の種類や、溶質の種類によって様々です。
では、溶け切らなかった塩化ナトリウムはどうしたら溶かすことができるでしょうか?
当然水を足せば溶かすことができる塩化ナトリウム量も増えます。
では、水を増やさずに溶かすためにはどうしますか?
イメージできるかと思いますが、水を温めてやれば溶け残っていた塩化ナトリウムも溶かすことができます。
つまり、溶媒の温度を上げると固体の溶解度は上昇します。
ちなみに、温度を上げた場合に気体の溶解度はどうなるでしょうか?
気体の分子は温度が上がるに連れ、分子運動が激しくなり飛び回ります。
そのため、溶媒から気体が外に飛び出していくため、溶解度は下がることになります。
ヘンリーの法則
ヘンリーの法則は《一定温度条件下において一定量の溶媒に溶ける気体の質量は圧力に比例する》という法則です。
つまり、圧力を掛けたら掛けた分だけ気体は溶媒に溶けるということです。